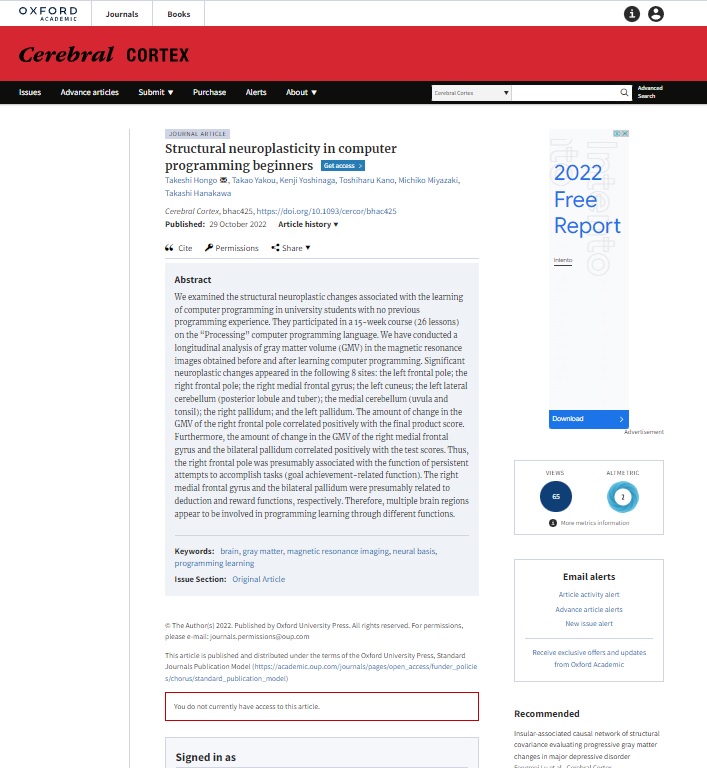本郷が担当する学習・研究を支援するサイト
 脳活動とプログラミング
脳活動とプログラミング

アルゴリズム/プログラミング
学習・教育
〇「プログラミングと脳研究」 の報告
学生の熱心な協力のもと進めて来た研究、「Structural neuroplasticity in computer programming beginners」が脳神経科学の国際学術雑誌Cerebral Cortex(Oxford ACADEMIC )に原著論文として掲載されました。
・プログラムを学ぶと脳の構造的変化が生じるのか?
・変化するとしたら、どの部位で変化が生じるのか?
・その部位の機能はどのような働きに関係しているのか?
このような研究課題を探るために始めた研究です。世界で初めて報告された成果です。
皆さんは、この質問に現在の段階でどのような回答があると思いますか?
結論のいくつかを以下に述べると
1)プログラミングを学ぶと粘り強くやり抜く力(目的達成機能)と関係する前頭極が強化される
2)演繹機能を司ると考えられる部位(内側前頭回)とプログラムのテスト成績と正の相関関係がある(プログラミングの学習で演繹機能がトレーニングされる)
3)報酬を予測し、意欲と関係すると考えられる部位(淡蒼球)とプログラムのテストの成績と正の相関関係がある(プログラミングの学習で学習意欲がトレーニングされる)
4)プログラミングの学習はさまざまな部位の協力によって行われている。
また、
原著論文は以下のサイトから入手できます。
https://doi.org/10.1093/cercor/bhac425
〇「プログラミングと脳研究」の第2報告 New!!
本郷らが国立精神・神経医療研究センターと共同で進めてきた研究が原著論文「Changes in functional brain activity patterns associated with computer programming learning in novices」として、脳神経科学の国際学術雑誌 Brain Structure and Function に掲載されました。研究チームは初心者のコンピュータ・プログラミング学習を反映する脳の局所活動の変化を調べるために、fMRIデータの縦断解析を行いました。その結果、①研究に参加した学生のプログラミング遂行精度は、後期段階に有意に向上したこと、②前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉皮質のさまざまな領域と、いくつかの皮質下構造(尾状核および小脳)が、プログラミング作業中に活性化していたこと、③右下前頭回における脳活動は、後期により大きくなり、課題遂行能力の向上と有意に相関したこと、④左下前頭回でもプログラミング課題中に高い活動が見られたが、学習による活動の変化と課題成績の向上との間に有意な相関は見られなかったこと、などが明らかになりました。
これらのことから結論として、初心者のコンピュータ・プログラミング学習は、右下前頭回内の機能的神経可塑性を誘発するが、左下前頭回(ブローカ野)内の機能的神経可塑性は誘発しないということを世界に先駆けて明らかにしました。
脳を対象としたプログラミング教育の研究は限られており、効果的なプログラミング学習法の確立には至っていません。今回の知見は、右下前頭回の活性化に着目した今後の教育法の開発に貢献できる可能性があります。
上述した脳とプログラミングの研究成果の概要とそこから考察される「プログラミング教育の意義」についての講演要旨です。ダウンロードしてお読みください。
〇 学校教育におけるプログラミング教育の必要性について(埼玉大学教育実践フォーラム2024)
試行錯誤しながら課題に立ち向かっていく粘り強さや意欲などの汎用的能力はプログラミング教育で育むことができる可能性のあることを、脳神経科学の成果から論考した講演要旨です。我々が行ってきた脳科学的アプローチで明らかにした研究成果と他の先行研究の成果とを改めて教育的な能力形成の観点から再考した要旨です。ダウンロードしてお読みください。
〇 日本情報科教育学会「優秀実践賞」を受賞 New ! !
2023年7月に学会発表した「プログラミング学習の進展に対するアンケートと脳灰白質容積の可塑的変化からの考察」が第16回全国大会優秀実践賞を受賞しました。プログラミング学習の初心者に生じた脳部位のGMV変化量と自己評価の間に有意な関係の存在することを明らかにしました.この種の研究はまだ無く、大規模な脳の学習研究に基づくデータを提示したことが評価されたものと受け止めます。学習に対する自己認識と脳の可塑的変化の関係を検討する先駆け的な成果です。
〇 日本産業技術教育学会 発表 New ! !
2024年8月17日に学会発表した「プログラムを学ぶ教育的意義の検討 ー脳神経科学からの知見ー 」の発表資料の一部を掲載します。本学会は日本におけるプログラミング教育を推進する中心的な学会の一つです。発表後には、会場の参加者から多大な反響があり、質疑応答が活発に行われました。本研究のさらなる発展を期待する意見が絶えませんでした。そこで、発表に使った提示資料の一部を掲載します。
〇 教科「情報」を学ぶ意義についての考察
論文 「情報的な見方・考え方を構成する枠組みと中心概念の提案」(日本教科教育学会誌 原著論文 2017)
高等学校における共通教科情報科が育成したい固有の資質・能力を,日本学術会議が提案する「新しい学術の体系」やイギリスのICT教育の改訂を支える考え方等の考察を通して,一つの試案として提示するものである。本提案では「情報を軸としてさまざまな事象を捉えようとする見方・考え方の育成」を「情報的な見方・考え方の育成」と呼ぶ。「情報的な見方・考え方」の定義では,日本学術会議が提案する「認識科学」や「設計科学」の領域を基礎として,各領域の下に情報的な見方・考え方の中心概念を配置する構造化を行った。本提案が採用した手法は,「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会― 論点整理― 」において主張された手法であり,その手法に基づいて構造化された本提案は,共通教科情報科が育成したい固有の資質・能力の具体的な試案と位置づけることができる。
論文 「英国のICTカリキュラム改訂の背景と日本の情報教育の枠組みに関わる基礎的研究」(教育情報研究 原著論文 2015)
本研究は, 英国のナショ ナルカリキュ ラム(以下NCと する )の 改訂へ 影響を与えたと 考えられる王立協会の プロ ジェ クト研究報告書を読み解き, 改訂の 背景を整理 し, 我が国の情報教育の 基本的方向性を検討するための知見を得ることを目的としてい る.その 結果,NCの 改訂では 以下の ような 視点から 検討が進めたことを読み取ることがで きた.すなわち,(1)イノベ ーションの創出を図る視点, 必履修教科とする意義は世界を認識し,理解する新たな 「考え方」を育成するとい う教育的な視点, (3)本教科が認識科学と設計科学の両面を併せ持つ とする学問的な特徴を捉えた視点, (4)ICTの 概念が 広過ぎるこ とと相まっ て, 汎用的能力育成に傾斜し過ぎたとする批判的な視点, などである.こ れらの 視点は ,我が国の今後の情報教育の枠組みを検討する上での知見として 示唆に富むものである.